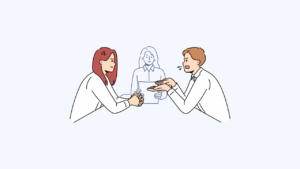理学療法士が職場で信頼されるためのコーチングスキル
「患者さんとの関係は良好なのに、職場の同僚や上司、後輩とうまく関われない…」
「後輩を指導しても思うように伝わらず、信頼を得られていない気がする…」
理学療法士として現場に立つ中で、こんな悩みを抱えていませんか?
実は、その原因の多くは“技術力の問題”ではなく、関わり方=コーチングスキルにあります。
本記事では、理学療法士が職場で信頼されるためのコーチング術をわかりやすく解説します。
読むことで、
- 後輩指導がスムーズになり、チームから頼られる存在になれる
- 同僚・上司との人間関係が改善し、ストレスが減る
- 患者指導にも応用できるコミュニケーション力が身につく
というメリットが得られます。
「人間関係に悩んでいる理学療法士の方」や「これからコーチングに挑戦してみたい方」は、ぜひ参考にしてください。
なぜ理学療法士にコーチングスキルが必要なのか?
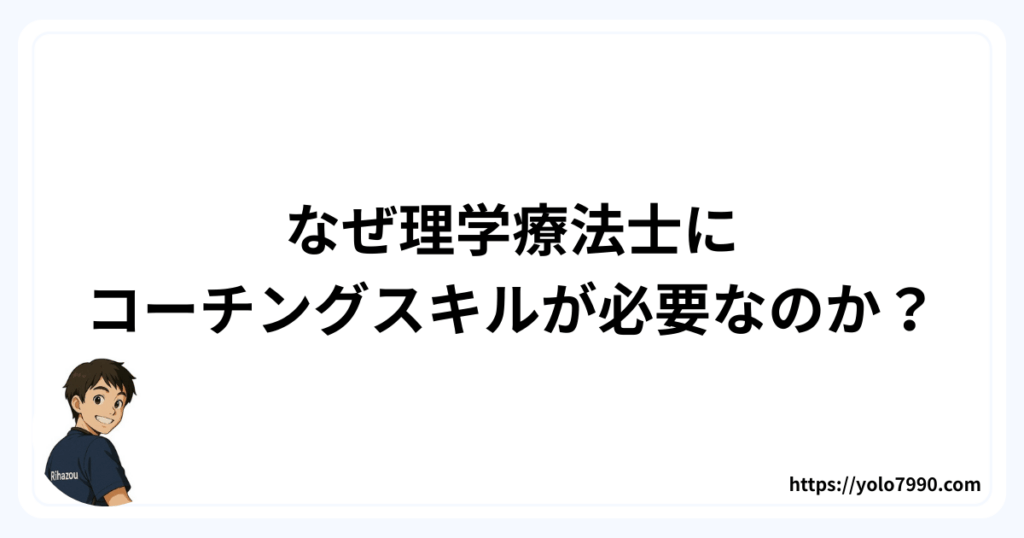
理学療法士の仕事は、患者さんと1対1で関わるだけではありません。
医師・看護師・作業療法士・言語聴覚士など、多職種と連携し、チームで患者のゴールを目指すことが基本です。
このとき、信頼関係がなければ必要な情報が共有されず、治療の質が下がるだけでなく、患者さんに不利益を与えるリスクもあります。
信頼関係がない職場では、次のような悪循環が生まれます。
- 必要な情報が回らない
- 小さなミスが大きな問題に発展する
- 人間関係が崩れ、離職につながる

「患者さんとの関係は良好なのに、職場の人間関係がつらくて辞めたい…」
こうした悩みは珍しくありません。
実際、人間関係を理由に退職する理学療法士は少なくないのです。
この問題を解決するカギが、コーチングスキルです。
相手を尊重し、引き出し、動きたくさせる技術を身につけることで、状況は大きく変わります。
- 他職種との連携がスムーズになり、信頼される
- 後輩指導がうまくいき、チーム全体の成果が上がる
- 人間関係のストレスが減り、離職を防げる
コーチングは「人を育てる技術」ではなく、
「チームを強くするための土台」と考えましょう。



コーチングスキルは、職場の空気を変え、医療の質を底上げする力があります。
よくある失敗|信頼を失う理学療法士の特徴
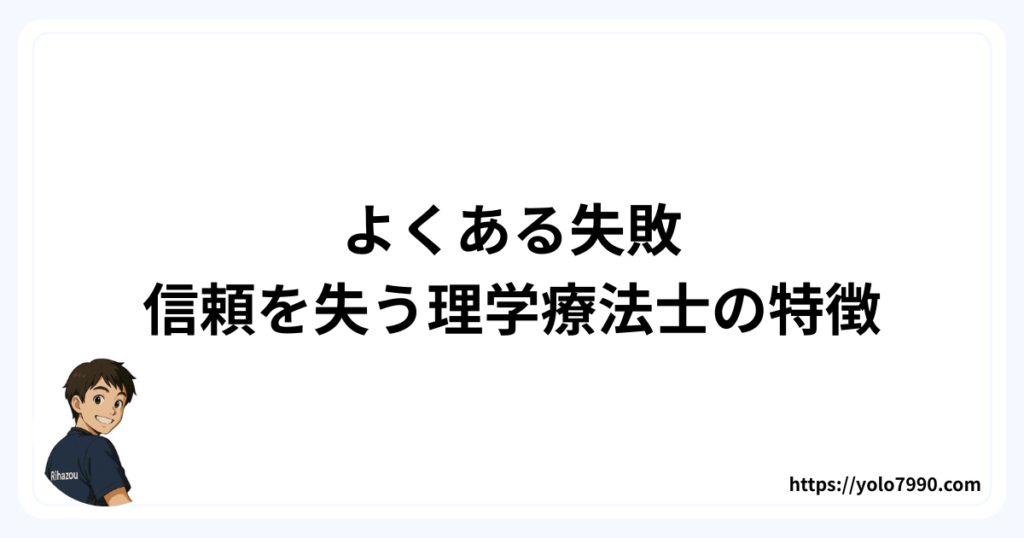
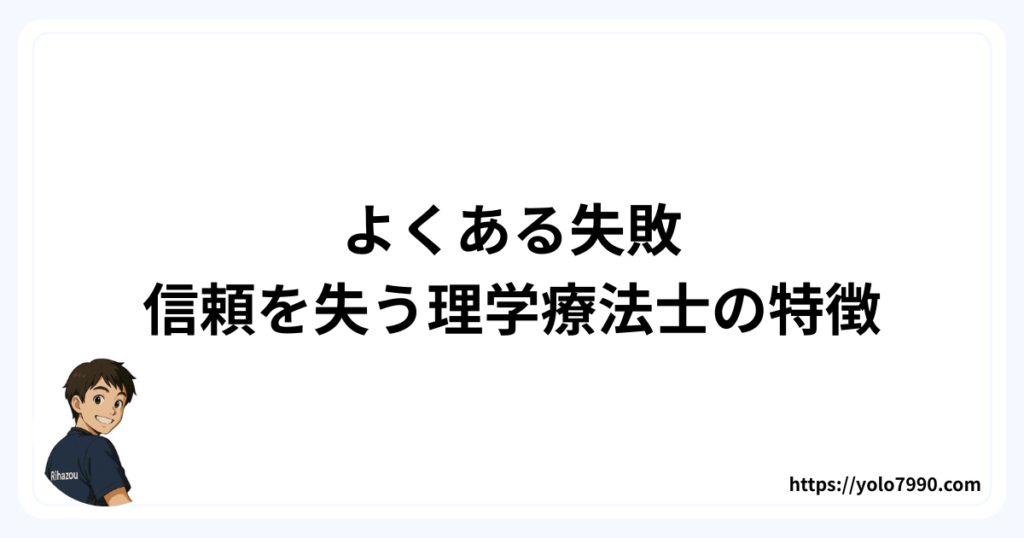
信頼を得られない理学療法士には共通点があります。
気づかないうちにやってしまっていると、
周囲からの信頼を失い、孤立する原因になってしまいます。
以下の5つに注意していきましょう!
1.話を最後まで聞かない
患者さんや同僚の話を途中で遮ったり、
「それはこうでしょ」と先回りして答えを出したり。
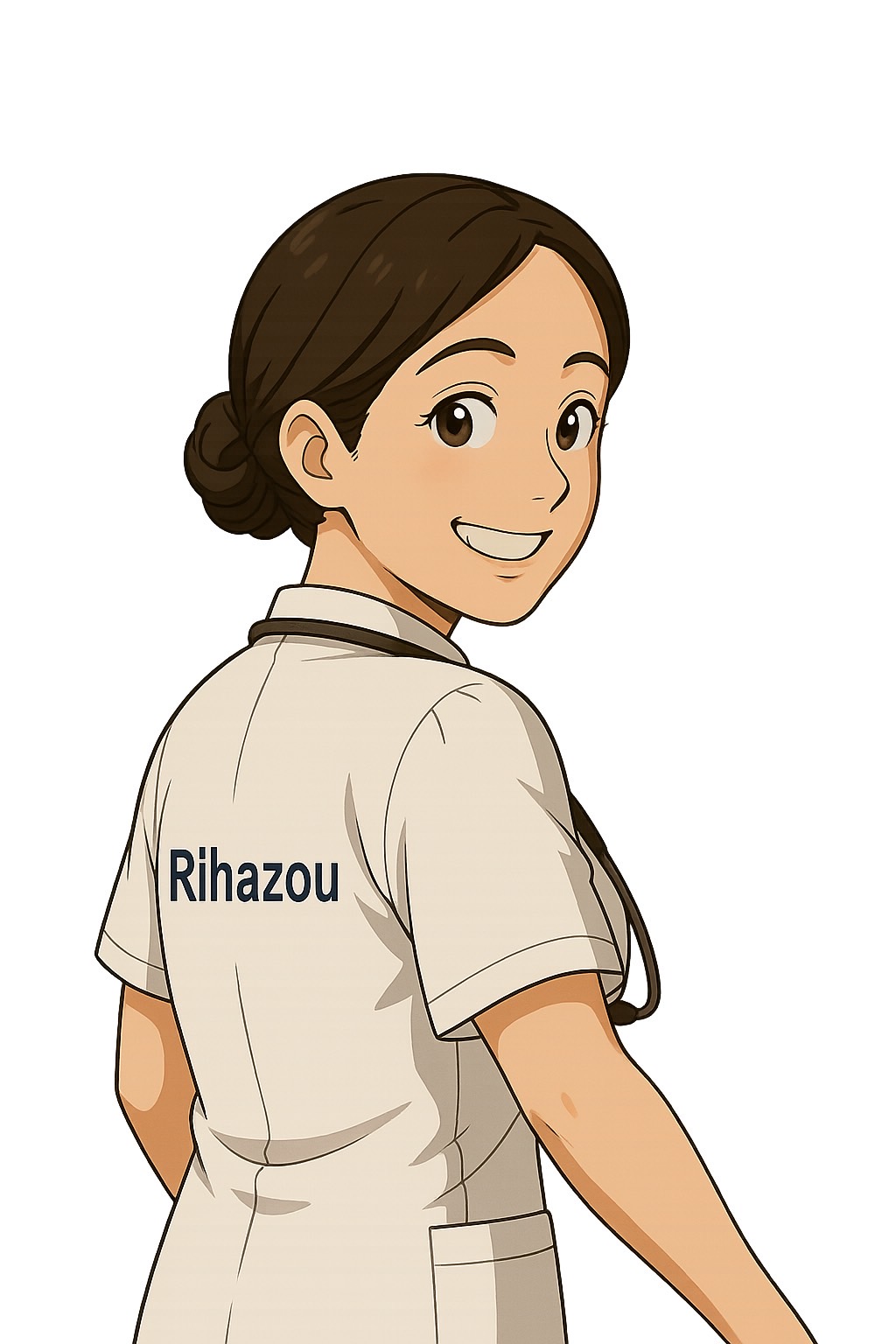
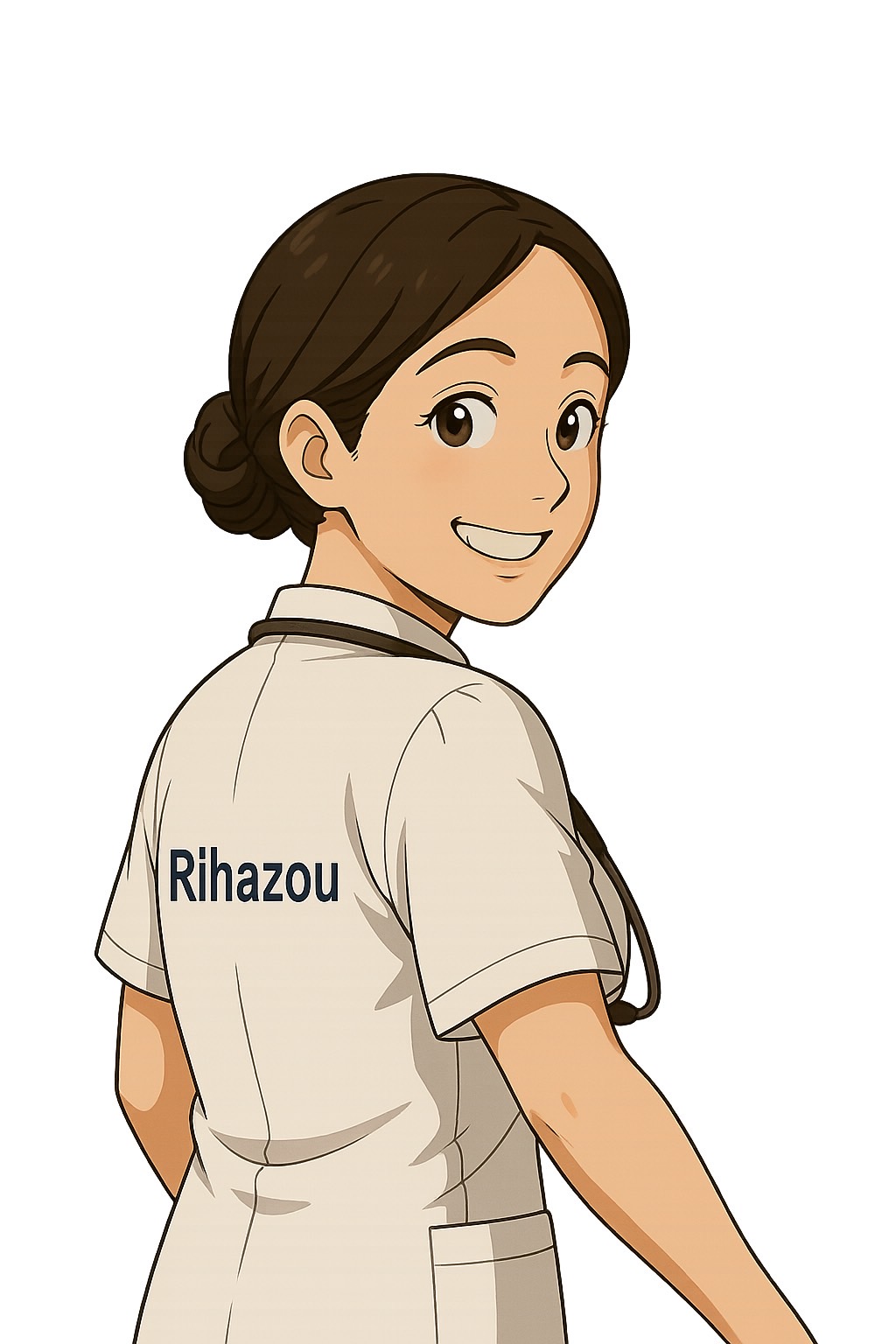
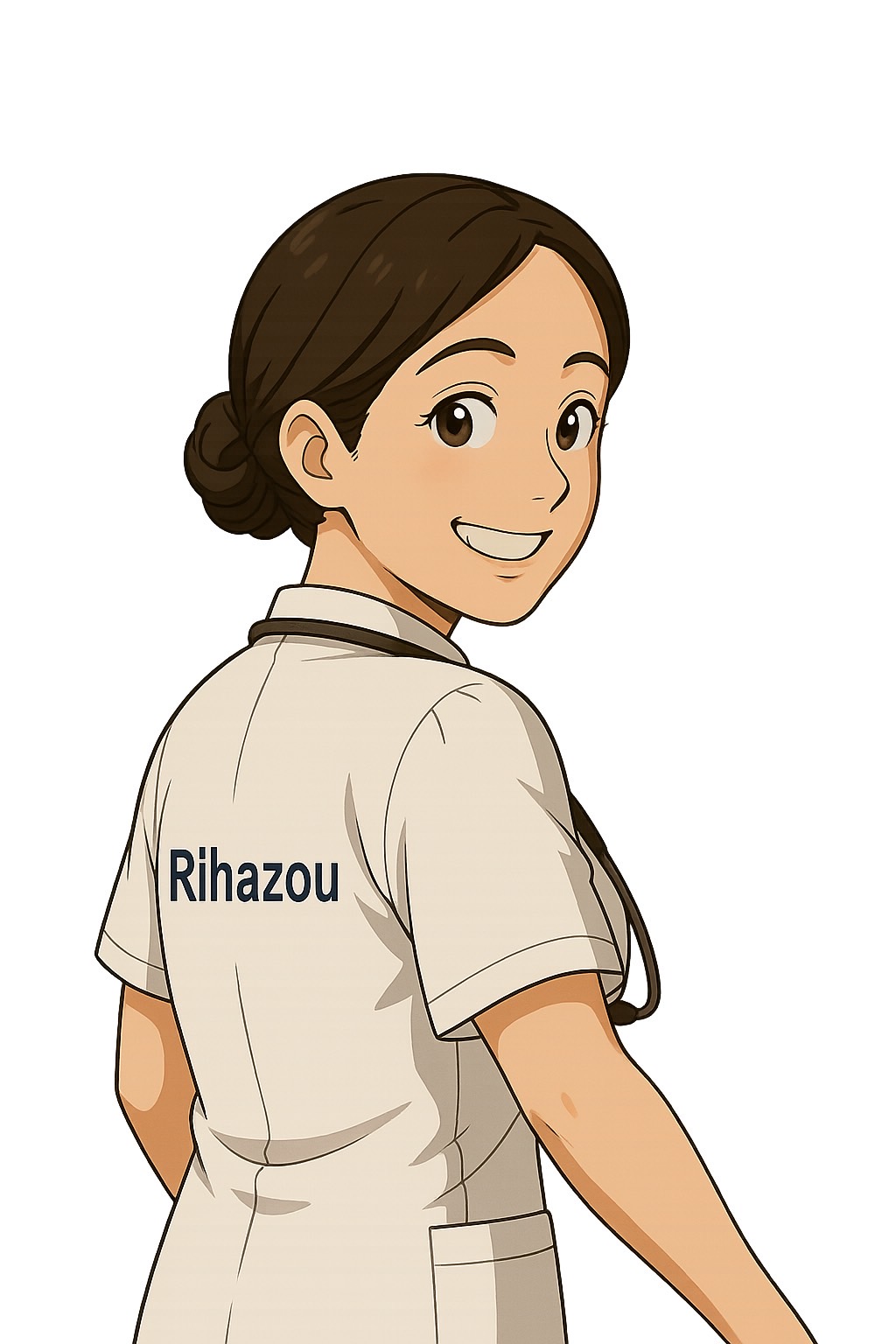
「どうせこういうことでしょ?」
これでは「聞いてもらえない人」という印象になり、信頼はどんどん薄れます。
承認・感謝の言葉がない
「ありがとう」「助かったよ」の一言が言えない。
成果を認めず、できなかった部分ばかり指摘する。
- モチベーションが下がる
- 自分の評価まで悪くなる
承認のない職場は、居心地が悪くなり人が離れていきます。
報連相ができない
「自分の判断でいいと思った」「忙しかったから伝えなかった」
こうした報連相の不足は、小さなミスを大問題に変える要因です。



「言わなくてもわかるだろう」
この言葉は、絶対に使わないようにしましょう!



萎縮して発言ができなくなります
後輩をコントロールしようとする
「こうしろ」「なんでできないんだ」と指示や否定ばかり。
これでは後輩は萎縮し、信頼関係どころか反発を招きます。
- 自主性が育たない
- チーム全体の成長が止まる
ボスマネジメントは信頼を失い、離職率をあげるので注意しましょう。
感情をそのまま出す
忙しさやストレスを言葉や態度に出してしまう。
「機嫌が悪い人」と思われると、報告・相談すら避けられます。



「今話しかけたら怒られそう…」
このような感情を抱かせないように自分から積極的に話しかけてあげましょう。
理学療法士が信頼を得るためのコーチングスキル
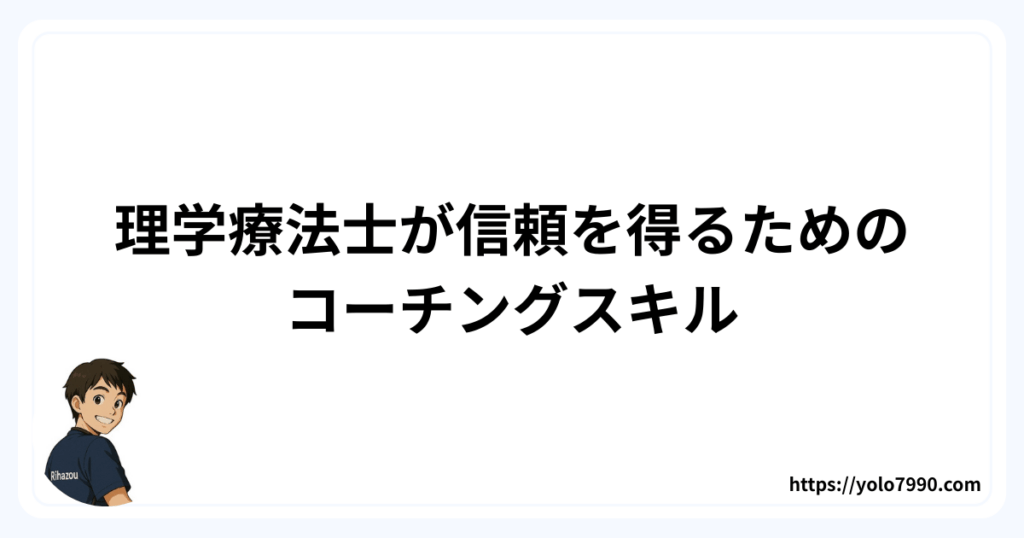
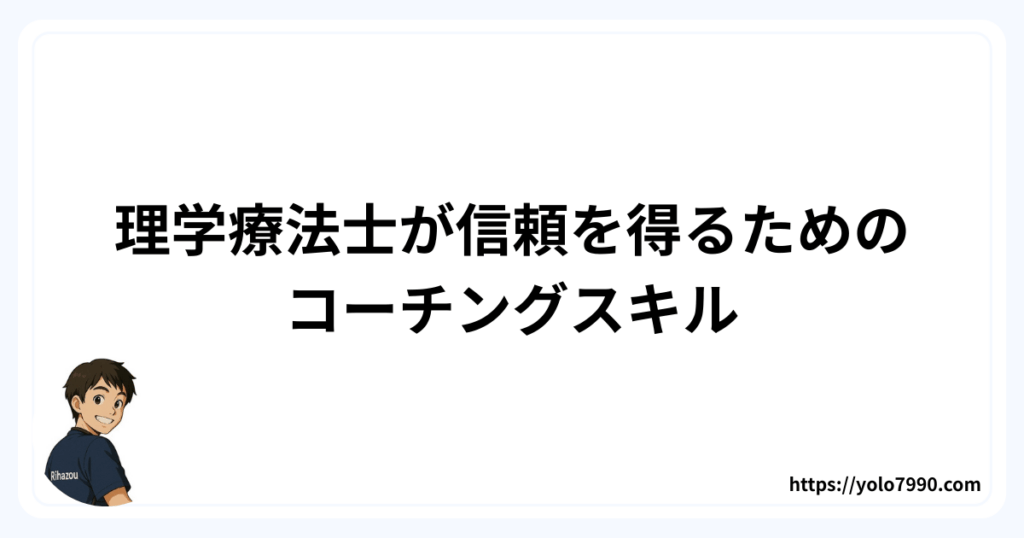
信頼される理学療法士になるために、まず意識しておきたいのが「3K」と呼ばれる関わり方です。
「3K」とは、次の3つの姿勢を指します。
- 傾聴(けいちょう)
:相手の話を最後までしっかり聞く
- 共感(きょうかん)
:相手の気持ちに寄り添い、理解を示す
- 肯定(こうてい)
:相手の存在や考えを認める
これらを実践するだけで、相手の心は大きく開かれます。
特に現場では、「とにかく話を聞く」ことを優先するだけでも、自然と人間関係が円滑になり、信頼される存在になっていきます。
「相手の意見が間違っている」と思っても、まずは受け止める姿勢を持つことが大切です。
後輩指導に活かす「リードマネジメント」
次に重要なのが、「リードマネジメント」という考え方です。
これは、指示命令で動かすのではなく、相手が自ら動きたくなるような関わり方を指します。
- ゴールを一緒に設定する
- 進捗を確認するときは「できたこと」から伝える
- 小さな成功を一緒に喜ぶ
この3つを繰り返すことで、後輩は自信を持ち、自発的に動けるようになります。
声かけ例:
×「どうしてできなかったの?」
〇「ここまではできたね。次は何が必要だと思う?」
こうした質問型の関わり方が、信頼と成長を生み出します。
SMARTゴールで明確な目標を立てる
後輩指導や自己成長の場面でよくあるのが、「もっと頑張って」や「しっかりやろう」という抽象的な指示です。
しかし、これでは何をどの程度頑張ればいいのか分かりません。
そこで活用したいのが、SMARTの法則です。
- Specific(具体的)
- Measurable(測定可能)
- Achievable(達成可能)
- Relevant(職場の目的と関連)
- Time-bound(期限付き)
例えば、
「評価がもっとできるようになろう」ではなく、
「今月中に歩行評価を5例担当し、終了後に上司からフィードバックを受ける」
といった具体的な目標にします。
このように設定すると、達成基準が明確になり、指導する側も評価しやすくなります。
DISC理論でタイプに合わせた対応
相手の性格や行動特性を理解することも、信頼関係を築く上で欠かせません。
その際に役立つのが、DISC理論です。
- D(主導型)
結果重視。結論を先に伝えると効果的
- I(感化型)
感情豊か。ポジティブなフィードバックが有効
- S(安定型)
協調性重視。安心感を与える対応を
- C(慎重型)
分析的。根拠やデータを提示すると納得する
「なぜこの人には話が伝わらないんだろう…」と思ったら、
まずは相手のタイプを考えてみましょう。



伝え方を少し変えるだけで、関係性は大きく改善されます。
信頼される理学療法士チェックリスト(コーチング能力の目安)
-1024x538.png)
-1024x538.png)
下記の項目について、自分でチェックを入れてYes/Noで確認してみましょう。
- ☐ 相手の話を最後まで聞くことができる
- ☐ 「ここまでできたね」「よく考えたね」と成果や努力を認めている
- ☐ 言動にブレがなく、一貫性を持って接している
- ☐ 相手の立場や気持ちを考えて行動できる
- ☐ 小さな約束や期限を守ることができる
- ☐ 感情的にならず、冷静に対応できる
- ☐ 必要な情報を積極的に共有している
- ☐ 後輩や同僚の意見に耳を傾け、反映できる
- ☐ チーム全体の成果を意識した行動ができる
- ☐ 相談や質問に対して、丁寧かつ分かりやすく対応できる
- 8個以上が☑
→ コーチングができている証拠
- 5〜7個が☑
→ 基本はできているが、改善の余地あり
- 4個以下が☑
→ コーチング力を強化したほうがよい
チェックが少ない項目から意識して改善してみましょう。



小さな積み重ねが、信頼される理学療法士への近道です。
今日から実践!信頼される理学療法士の1日チェック表


「自分の行動、信頼される理学療法士にふさわしいかな?」
「どこを改善すればもっとチームに貢献できるだろう?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
信頼関係は、特別なことではなく、毎日の小さな行動の積み重ねで築かれます。
だからこそ、自分の行動を振り返り、改善点を見つけることが大切です。
そこで役立つのが、この『信頼される理学療法士の1日チェック表』。



今日からチェックしていきましょう!
毎日の行動に✓をつけるだけで、信頼される習慣が自然と身についていきます。


コーチングを日常に取り入れるコツ|理学療法士が信頼されるために


「コーチングって難しそう…」
「忙しい現場で意識している時間なんてない」
そう感じている理学療法士は少なくありません。
コーチングは特別な時間を作らなくても、日常のちょっとした関わりに組み込むことが可能です。
「聴く」を優先する
コーチングの基本は「傾聴」です。
仕事が忙しいと、つい「早く答えを出す」「指示を出す」ことに意識が向きがちですが、
相手の話を最後まで聞くことが信頼の第一歩です。
- 相手の言葉を遮らない
- 話の要点を要約し、理解を確認する
- 「それでどう思った?」「他に案はある?」と質問で引き出す



「なるほど、そう考えたんですね。じゃあ、どう進めたいと思いますか?」
このように傾聴し、相手の意見を引き出すのがポイントです。
フィードバックは「できたこと」から伝える
コーチングでは「承認」が欠かせません。
いきなり改善点を伝えるのではなく、まず相手の努力や成果を認めることが大切です。
- 「ここまで準備してくれたのは助かった」
- 「評価の結果、患者さんの変化に気づいたのは良かった」
この一言で、「聞く耳」を持たせる雰囲気が生まれるのです。



「この部分はよくできていたよ。じゃあ次はここを工夫してみようか。」
承認し、次なる課題を与えるようすることがポイントです。
小さな目標を一緒に設定する
大きなゴールを設定しても、達成までの道のりが見えなければ動けません。
短期間で達成可能な小さな目標を立て、進捗を一緒に確認しましょう。
- 「今週は患者さんのROM評価を3件担当してみよう」
- 「1日1回、フィードバックを自分からもらう習慣をつけよう」



達成感の積み重ねが、自主性とやる気を育てます。
DISC理論を活用して伝え方を変える
相手によって響く言葉は違います。
DISC理論を参考にすると、タイプ別に適したアプローチができるようになります。
- 主導型(D):結論を先に、スピード感重視
- 感化型(I):ポジティブな表現、盛り上げる
- 安定型(S):安心感を与える、変化はゆっくり
- 分析型(C):根拠・データを提示、丁寧に説明
「振り返り」を日課にする
1日の終わりに、自分の対応を振り返ることでコーチング力は格段に上がります。
- 「今日は相手の話をちゃんと聞けたか?」
- 「成果を承認する言葉を伝えられたか?」
- 「改善点は次にどう活かせるか?」



「よし、今日は傾聴ができた!明日はフィードバックの質を上げよう」
よくある質問(Q&A)|コーチングを現場で活かすために
|コーチングを現場で活かすために-1024x538.png)
|コーチングを現場で活かすために-1024x538.png)
まとめ|理学療法士が職場で信頼されるコーチングを日常に
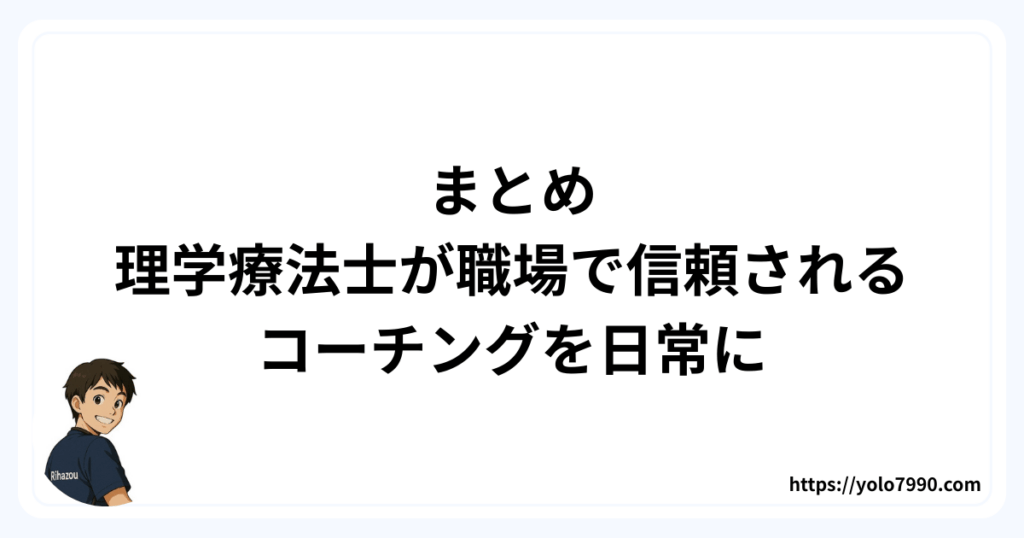
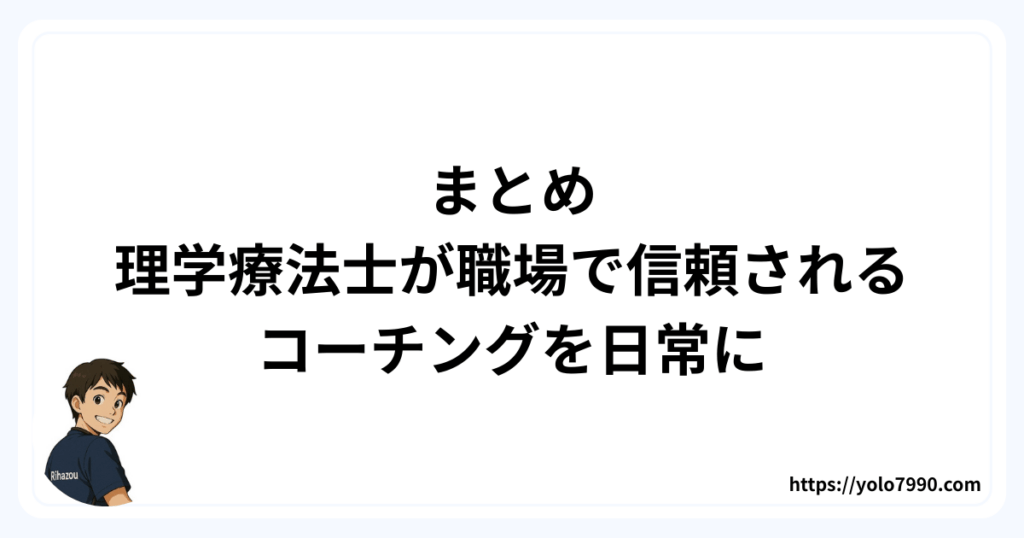
理学療法士として働く中で、
「患者さんとの関係は良好なのに、職場ではうまくいかない…」
そう感じる方は少なくありません。
その多くの原因は、コミュニケーションの質と信頼関係の不足にあります。
本記事では、
- 傾聴・共感・肯定の「3K」
- 相手を動かす「リードマネジメント」
- SMARTな「目標設定」
- タイプ別対応の「DISC理論」
といった具体的なコーチングスキルをご紹介しました。
これらを実践することで、
- 後輩指導がスムーズになり、チームから頼られる
- 同僚や上司との連携が強まり、ストレスが減る
- 患者指導にも応用できるコミュニケーション力が身につく
といった大きなメリットが得られます。
ポイントは、特別なことをするのではなく、日常に取り入れること。
「まずは話を最後まで聞く」「1日1回、承認の言葉を伝える」
こんな小さな一歩が、あなたの職場での信頼を確実に変えていきます。
行動しなければ、何も変わりません。
今日から1つだけでも実践してみましょう。
その積み重ねが、あなたを「信頼される理学療法士」に導きます。